自動車のメカニズムは日進月歩で、さまざまなメーカーが技術革新を進め、新しい仕組みを次々と生み出している。トランスミッションについてもそれは同じ。その中でも特にオートマチックトランスミッションの進化は目まぐるしいものがある。
ここではその中から、スポーツ系車種に搭載例の多い「DCT」に焦点を当てて少し掘り下げていきたい。
AT=オートマチック・トランスミッションとは
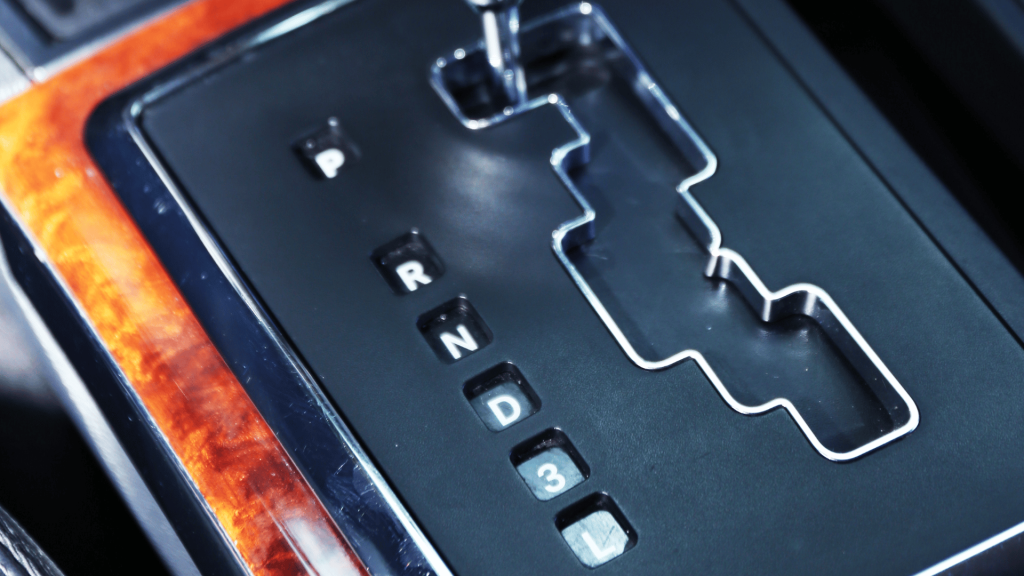
DCTの話に行く前に、まず基本のオートマチックトランスミッションについて触れておこう。
ATとMTの違い
本記事を読んでいるクルマ好きであれば、すでにご存じかもしれないが、オートマチックトランスミッション(以下AT)というのは、変速を自動でおこなってくれるトランスミッションのこと。
操作は、シフトレバーを走行レンジに入れてブレーキを離してからアクセルを踏むだけ。つまり、変速に必要なシフト操作やクラッチペダルの操作が不要となっている。
ATの仕組み
一般的なATは、マニュアルトランスミッション(以下MT)と同じく、各速度域に応じたギヤが備わっていて、その切り替えを専用の機構でおこなっている。クラッチの代わりになるのは「トルクコンバーター」と呼ばれる機構が受け持つ。
その仕組みは、オイルが満たされたドーナツ状の部屋に、エンジン側の軸とAT側の駆動軸にそれぞれ接続された円盤が交互に配置され、その円盤に生えた細かいフィンがオイルをかき混ぜることで、駆動力がエンジン軸からAT側の駆動軸へと滑らかに伝達されるという構造である。
エンジンからの駆動力はそのオイルの粘度でわずかに伝わっているので、ブレーキを踏まないと、アイドリングの回転分だけ前に進む。これをクリープ現象という。
一般的なATの優れた点と欠点
一般的なATは、実際のギヤ段で変速が行われているため、大排気量やターボエンジンの大きなトルクにも耐えられるという点がまずメリットとして挙げられる。トルクコンバーターも容量を増やすことで対応が可能。
そして、加速時や高速走行時など、高トルクが必要な場面でも駆動ロスが少ないことから、特に高速巡航時の燃費が良いという点も大きなメリットとなる。対して欠点は、変速が自動でおこなわれることでの加速感の不連続性と、加速トルク発生の遅延があること。
あくまでも変速のタイミングはATのコンピューター任せなので、ドライバーの意向と合わない場合もあり、アクセル操作が頻繁に変化する山道やサーキット走行では、意図通りの変速が行われず、不満を感じることも多い。
また、トルクコンバーターを介することから、スポーツ走行時などではその駆動力の伝達においてダイレクト感が不足するため、物足りなさを感じる場合もある。
DCTとはどんなもの?

「DCT」とは「Dual Clutch Transmission(デュアルクラッチトランスミッション)」の略で、その名のとおり、2系統のクラッチを備えるトランスミッションである。
そのアイデアは1970年代に生まれたとされていて、1980年代にレース用の機構として「ポルシェ」と「VW」グループの共同開発で実用化された。市販車に初めて採用されたのは、2003年に発売された「VW ゴルフ R32」(名称は「DSG」)である。
DCTの仕組み
簡潔に説明すると、MTのクラッチ操作を専用のクラッチ機構で肩代わりして、変速と共に自動で制御するというもの。基本的な構成は、ギヤの組み合わせを奇数段と偶数段の2系統に分け、それぞれにクラッチを装備するというもの。
同軸状にギヤが連なる構成のMTでは今のギヤを抜いてから次のギヤに入れ替える必要があるが、DCTでは2系統に分かれていることで常に次のギヤが噛み合った状態にできるので、クラッチを切り替えるだけで変速が完了する。
クラッチ機構は、オイルに浸されている湿式と、浸されていない乾式の2種類に分けられる。それぞれメリットとデメリットがあるので、車種や用途で使い分けられている。
DCTのメリット
DCTの最大のメリットはそのシフトアップの速さにある。MTでは先述のようにギヤを入れ替える操作が不可欠だが、DCTではクラッチ操作のみで変速がおこなえるため、回転を合わせるための最小限の時間で変速を済ますことができる。そのため、スポーツ志向の強い車種に多く採用されている。
また、トルクコンバーターを介さないため、ダイレクトな変速フィールが味わえることも特色のひとつ。そしてトルクコンバーターによるロスがないため、燃費の向上にも寄与する。
DCTのデメリット
DCTはその構造上、どうしても複雑になりやすいため、耐久性の問題やメンテナンスのコストが多く掛かるなどの欠点があるとの指摘がある。日本では、市街地の信号の多さやアップダウンの多い地形、そして慢性的な交通渋滞などからクラッチへの負担が大きく、
特にAT(トルコン式)の感覚でノロノロ運転するとクラッチのトラブルを招いたり、寿命を短くしたりすることが懸念されているため、欧州と比較して採用例は格段に少ない。
DCTの種類
DCTは、それを開発した各メーカー毎に細かくタイプが分かれていて、名称も異なるケースも多い。先述のようにクラッチ機構の種類は湿式と乾式に分かれているし、そこにトルクコンバーターを追加し、発進時の滑らかさを高めたタイプも存在する。
DCTを採用している主な車種

ここでは、DCTを採用している主な車種を紹介していく。
フォルクスワーゲン・ゴルフR32
量産車で初めてDCTを採用したのは、2003年に発売された「ゴルフR32」である。フォルクスワーゲンは、ポルシェと共に早期からDCTの開発をおこなったパイオニアで、レースでのノウハウを持っていたため、発売からしばらくは専売特許のようにその強みを維持していた。
ポルシェ・911カレラ
レースの強者として常に新しい技術の開発に取り組んでいたポルシェは、DCTのアイデアをフォルクスワーゲンに持ち込み、共同で開発することになった。レースではしっかり結果を残したが、市販車にそれが採用されたのは「ゴルフR32」に遅れること5年の2008年だった。
それだけ熟成を重ねて満を持してリリースされた「PDK(Porsche-doppelkupplung)」と名付けられたそのシステムはポルシェにふさわしい性能を発揮した。MTに煩わしさを感じていた層にも支持され、トランスミッションの選択肢の大きな柱になった。
三菱・ランサーEVOⅩ
三菱で初めて市販車にDCTが採用されたのは、2007年に発売の「ランサー エボリューションⅩ」で、「ポルシェ」より1年早い。
「TC-SST(ツインクラッチ・スポーツシフトトランスミッション)」と名付けられたそのシステムはゲトラグによって開発されたもので、湿式のクラッチを直列ではなく並列で配置することで、ターボの大トルクに対応している。
日産・GT-R
2007年に発売された日産・GT-Rも独自開発のDCTを採用している。究極の市販スポーツカーを目標に掲げた「GT-R」はミッションも最高性能を求め、変速スピードが最速のDCTを採用。
クラッチはボルグワーナー製のものを採用しているが、ギヤなどは日産グループで製造。0.2秒の変速(UP)スピードを実現するとともに、専用のオイルクーラーを装備して高い耐久性も実現している。
三菱ふそう・キャンター
2010年に発売された三菱ふそう・キャンターは、トラックで初めてDCTを搭載したモデルである。機構は通常のDCTと同じで、トラックの高い負荷にも耐える大容量クラッチなどを備えるのが特徴。
変速の継ぎ目が少なく、スムーズな加速が可能であるが、採用の目的は、燃費の向上に重きが置かれている点にある。
ホンダのi-DCDについて
2022年の末頃にホンダのi-DCD搭載車が、急カーブの連なる山道や高速道路の渋滞で立ち往生する事例が多発し、クルマ業界を賑わせたのは記憶に新しい。「i-DCD」はハイブリッドと7速DCTを組み合わせたホンダ独自のシステムである。
トランスミッションは2速から7速で、1速に相当する領域はモーターが担当し、市街地から高速道路までの広いレンジで低燃費を実現するシステムである。確かに優れたシステムではあるが、設計またはテスト工程に抜けがあり、トラブルが多発した。
発進はモーターでおこなうが、長時間のノロノロ運転ではバッテリーが枯渇する。そうなると動力がエンジンに切り替わるが、モーターが受け持つ1速は機能しないため、発進が2速からとなる。
これは設計上想定された挙動であるが、問題はクラッチが乾式であった点にある。半クラッチの頻度が高い2速発進を繰り返すことでクラッチに大きな負担がかかり、さらに冷却効率が低い乾式クラッチであるため、高温となりフェイルセーフが作動して走行不能に陥るという事態が発生した。現行車種ではこの問題が改善され、2モーター式のe:HEVに移行している。
DCTの最大の魅力は、鋭くスムーズな変速とダイレクトな加速フィールにある。スペックだけでは伝わりづらいその特性を実感するには、実際に乗って体感するのが最も確実である。DCT搭載車の実力に興味があるなら、「おもしろレンタカー」でのレンタルをおすすめしたい。スポーツカーを中心に、DCTならではの走行フィールを存分に楽しめるラインナップが揃っているので、まずはその魅力に触れてみてはいかがだろうか。


